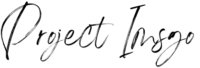頭痛がする。それが気圧によるものか、ストレスによるものか、はたまた眼精疲労によるものかは判然としないが、不快な違和感として意識の片隅に痛みが居座る。
家には復調した妻と、娘が帰ってきた。独りの家から、ふたたび家族の家になった。
随分と遠くに来たもんだと思う。過去を想起するとき、そんな表現がよく使われるが、たしかにそんな感じがある。
学生時代に中野に一人暮らしをしていたころ、僕はひたすら曲を作っていた。
その年、大学を留年した僕は、春に社会へ出ていった友人たちに置いていかれて独りになった。サークルの後輩たちはそれでも僕に来てほしいと言ってくれたが、区切りとして、けじめとして、僕はその場所を後にした。
引き止める好意を無下にして孤独になった僕は、それでも追いすがってくる影との共同生活を始めることになる。一人暮らしではあるが、そこには僕という人間以外にも何かしらの存在がいた。
今もまた、影が自分を脅かしているが、当時と今ではその正体が違う。かつて僕を脅かしていたのは、過去の記憶だった。被虐者としての記憶が、あの頃の僕の背後霊だった。
そういうものに抗うすべを持たなかった当時の僕は、言葉でないものによって、背後霊へ抵抗を試みていた。それが例えば曲。
「ノート」というタイトルを付けたこのインストには、実はちゃんと歌詞がある。日の目を見ることはなかったが、自分の痛みをひたすらに書き綴り、それを「それでもいいんだ」と言ってやりたい気持ちを詩とした。だからタイトルの「ノート」とは、そういうものだ。
この曲を自分で聞くとき、いつも夜の町を思い出す。西武新宿線の沿線、住宅と街灯と、坂が多かった町。夜な夜な近くのコンビニで安いワインとかビールを買って、酩酊しながらその町を独りさまよっていた。
酩酊のなか、ぼんやりと広がる街灯の光は、まるで満開の桜みたいだった。幻想の夜桜を見ながら、僕は泣いたり笑ったりしながら深夜の町をフラフラしていた。側からは相当な不審者だったろうが、さいわい職質にあうことはなかった。
安酒のボトルが何本も転がる部屋に戻って、そのままソファで、あるいはトイレの床で眠った。そのときだけは、自分の存在を奪い去ろうとするものから、つかの間自由になれた錯覚に陥っていた。
朝が来ればまた独り。笑いあった友たちの去った世界に独り。孤独ではなく孤立。当時付き合っていた現在の妻と、彼女の家族の存在がなければ、僕は今どこにいたのだろうか。そもそも、いることができていただろうか。
孤立の最果ての、さながら崖のような場所での綱渡り。希死念慮にはなぐさめを、脅す影には命乞いをしながら、なんとか日々をやり過ごした。
その続きが今なのだと、今だからこそ思える。現在と過去は物理的には不可分だが、意識上でその連続性が必ずしも保持されないということを、僕は知っている。
思えば遠くに来たもんだ。そう思えるのはきっと、今とかつてが一本の時間線の上に並んでいるから。今があの日の続きだと知ったから。消えたい自分を慰留しながら生き延びた先が、家族と過ごす今なのだ。
痛みが過去のものとして、たんなる「思い出」となりうることを知っている。だが同時に、過去が過去でなく「今ここ」とコンフリクトすることも知っている。そして、追いすがる影に抗う手段を知っている。
だからこそ、仕事でもなく、社会的文脈とも関係なく、ただひたすらに内面世界をここに記す。これに意味は要らない。価値も要らない。ただ、自分のニーズに従って自分のためだけに書いている。
そういうことが、少しずつできるようになってきた。