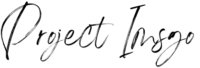ずっと心に焼き付いている心象風景がある。浪人時代、ある事情から上京し、通っていた予備校の借り上げていた物件に住んでいた頃の記憶。
東京のはずれにあったそこ。目の前の道路は道幅の割に交通量が多く、夢の島に向かうトラックの轟音に毎夜悩まされていた。
僕は浪人を罪悪だと考えていた。多くの期待、多くの応援、それらをすべて裏切った罪。その罰として、僕は浪人の1年間、見知らぬ土地で誰とも交流を持たずにひたすら受験勉強をしていた。
1ヶ月間声を発さずに生活すると声の出し方を忘れる。自分の声がどんなだったかを忘れる。そんなことを体験した。
部屋は4畳半か5畳くらい。ベッドと本棚と机と洗面台。それが部屋にあったもののすべて。西に面したベランダからは、いつも青空が見えていたような気がする。
他者と一切の交流を持たない。それは同時に、社会から、世界から自分を切り離す行為でもあった。僕は確かに生きてはいたが、その存在はひどく不確かで、仮にその部屋で僕が死んだとて、それに気づく者はいなかったかもしれない。
そうして気づいた。いや、悟った。人間とは、他者から認識されなければ存在していてもいなくても変わらないと。世界から切り離された存在を、世界が認識することはできない。その頃の僕は皮膚感覚としてそう考えていた。
僕はその部屋で、自分を再定義した。人間としての存在ではなく、勉強をするためだけの道具として。これは自分への罰でもあり、同時に必要なことでもあった。
生まれつきか、被虐待児におけるいわゆる「解離トレーニング」の結果か、僕の被暗示性はきわめて高かったようで、この暗示は強力に働いた。結果として24時間のうちの6割を勉強に当てるというあまりにもストイックな生活を実現した。
だがこんなことをして無事で済むはずがない。僕には浪人中の梅雨から秋までの記憶が一切抜け落ちている。いまだそれは復元されていない。どうやらそれが強力な外傷体験になっているようで、毎年夏になるとトラウマ反応として強い解離症状があらわれる。
結論だけ言えば僕は浪人に成功した。偏差値は一年で20上がり、現役時代ではおよそ不可能だった大学に進学することができた。両親には凄まじい経済的負担をかけたが、被害者意識の強かった僕は、それを幼少期の仕打ちに対する賠償金ぐらいにしか考えていなかった。
僕の暮らしていた701号室からは、よく空が見えた。もちろん曇ったり雨が降ったりはしていただろうが、不思議と青空しか覚えていない。白い壁に囲まれた部屋と、そこから見える青い空。世界から切り離されたことをこれでもかと実感させられた。
あの頃、僕は未来を拒絶していた。自分は志望校に合格したという事実さえ残せれば、そこで死んでも構わないと本気で思っていた。そこから先のことなんて知ったことじゃない。もし生きながらえるなら、その先は「その先の僕」が生を引き継いでくれるだろう。僕は本気でそう思っていた。だから大学に合格した時点で、僕の人生は一回確実に終わったのだ。
覚えているのは断片的な出来事と感情。当時付き合っていた高校の同級生に「家族みたいだから恋人と思えない」とかいう理由で振られたこと。自分みたいな出来損ないが近くにいると、大学生活を謳歌している友人たちの邪魔になると、自らすべての連絡先を消したこと。母と電話している時、激昂して携帯電話を叩き割ったこと。借り部屋のものは壊せないからと、代わりに自分の腕を切ったこと。東京の夏が地元のそれとまったく違うこと。空気がまるでゲルのような物理的質量を持つかのように、重く粘つく感触だったこと。
僕はずっとひとりで空を眺めていた。それにどんな意味があったかは、もうわからない。思い出せない。でもそのとき、僕は確実に虚無だった。ゼロですら表しようのないモノだった。世界にとって「ないもの」だった。そして、それは自分で望んでそうなったことだった。
今僕は確かに生きている。僕として生きている実感とともに。だがかつて自分でぶちあけた大穴は、未だブラックホールみたいに残り続けている。それは確かに痛みだった。痛くはなかったが、たしかに痛みだった。
いつか、あの夏のことをちゃんと思い出せるのだろうか。思い出したとして、そこにはどんなものがあるのだろうか。時折、あの部屋の風景を思うたびにそんなことを考える。