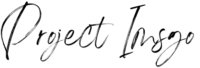祖父について語ることはそう多くない。というのも大半が「厳しかった」という印象だけで、記憶に残っているものが少ないからだ。だが家父長制の権化のような祖父が作り出した環境は、安定的な母親が傍にいたにもかかわらず、僕の愛着形成を阻害するには十分なものだった。
母は祖父、つまり父の家から結婚を反対されていたという。田舎の成金らしい卑小なプライドがそうさせたのだろう。家系図を見せろとも言われたのだとか。今思えば、そこで母が諦めてくれれば僕は存在せず、この苦しみも生まれることはなかったと思う一方で、喜びもなかったと思うと複雑な心境になる。
祖父は絶対的な存在だった。僕ら家族は同居していたが、祖父の部屋と僕らの居室は家の反対側で、祖父は僕らの居室だった6畳間には絶対に入ってこなかった。だから幼い僕と妹にとってはそこが結界で守られた絶対安全地帯のように感じられていたのを今でも思い出せる。
祖父には暴力を振るわれた記憶がない。だがどうやら単に記憶がないだけらしい。母が言うには、僕が2歳くらいの頃、何かのときに祖父が僕を鍋で殴ろうとし、母は身を呈してそれをかばったという。そういうことが日常的にあったのだ。幼児期に暴力を受けていたとしても何ら不思議はない。記憶にはないが、おそらく身体が覚えているだろう。
そんな祖父が死んだのは、弟が生まれた次の年、僕が小学4年生の春だった。
家族の居室だった6畳間のふすまのすぐ外、洗面所で祖父が倒れた。当時のことは未だにトラウマティックに覚えている。数メートルもない距離で父と母が必死に祖父を呼んでいる声、救急車のサイレンが家の前で止まり、救急隊員たちが駆けつける音、そしてその間泣いて震えながら抱きしめあっていた僕と妹。未だにサイレンの音が止まるのを耳にするのが怖い。
祖父が死んだ翌日から、徐々に父親の様子がおかしくなりはじめた。
僕のトラウマの大部分はそこから始まる。優しかった「お父さん」は、祖父の死とともに消えてなくなった。
父の病的な言動や行動、僕らきょうだいに対する虐待が始まったのはそれからだ。