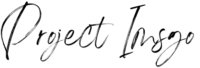「書くこと」の原点は虐待的な思い出からスタートする。
僕は父親に虐待を受けてきたが、祖父もまた厳格で前時代的で、虐待的な人間だった。家庭内で世代間連鎖が起こっていたと理解できたのは、大人になって随分経ってからだった。
祖父とは同居していた。そして祖父が存命の間は、父親からの虐待はほとんどないに等しかった。代わりに祖父が僕らきょうだいを虐待的に扱っていた。脳梗塞で倒れたことがあったらしく、半身が不自由だったから殴られることはなかったが、その分精神的な虐待を長く受け続けた。
1998年。僕の住む街でオリンピックが開催された。
学校では聖火ランナーの応援イベントや、今で言うところの「レガシー教育」、市の作文コンクールへの応募など、さまざまなものが授業のなかに取り入れられた。
そんななかで、祖父は作文コンクールで僕に賞を取らせたかったらしい。正確には「孫がコンクールで賞をとったという事実」がほしかったのだろう。僕の自信を育むとか、そういう気持ちは子どもごころに微塵も感じられなかったから。
祖父は僕にオリンピックの作文を書かせた。隣に張り付いてああでもない、こうでもないと口うるさく言うわけではない。気に食わないところは全部書き直させるとか、添削の名のものとに内容をコントロールしていたわけでもない。
僕がやったのは、祖父が原稿用紙に薄く書いた文章をなぞることだった。
屈辱は感じなかった。怒りも感じなかった。せいぜい小学2,3年生だった当時の僕は、祖父が言うならそれはすべきこととして実行した。子どもの字を使って、大人が作文を書いたのだ。
それを学校に提出してからややあって、校長から呼び出しを受けた。作文がコンクールで結構な賞をとったという知らせだった。それは当たり前だろう。だって大人が書いたんだから。
表彰式のことは今でも覚えている。
授業が終わってすぐ、母の運転する車で会場に向かったこと。オリンピックイベント用に設営された会場のステージの上で、市長から直接賞状を手渡されたこと。その賞状は長いこと額に入れられ、実家の仏間に飾られていたこと。
そして子どもだった自分は、「何も感じなかった」こと。
嬉しくも悲しくもない、感情が一切伴わない経験。今ならわかる。それは空虚という感触だ。
ただ虚しい。自分のことらしいが、特に何も感じない。
その時の僕はもしかしたら、静かに深い傷を負ったのかもしれない。
後年になって母とその話をした。
母は祖父のしたことを僕にとって良くないことだと思いながら、嫁いだ身として口を挟むことができなかったことを悔いていた。
そういう話を聞くたびに自分の内に眠る子どものパーツが不貞腐れながら言う。
「どうせ助けてくれないんでしょ」
母の立場や心情も十分理解できるが、僕はそれでも傷ついた。それが全てなんだろう。
書くこと、書いたものを人に評価してもらえること。
その出発点がこれだ。
そしてこの記憶は、虐待の記憶の序章の一番最初でもある。