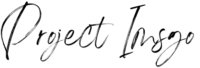祖父が死んだあと、父は変わった。
はじめに父がしたことは、外につながる家中の出入り口にセンサーを付け始めたことだった。玄関を開けるたびにコンビニの入店音みたいな音がするのが、子ども心にすごく嫌だったのを覚えている。まるで軟禁されているような気分だった。
また父は徐々にスピリチュアリズムに傾倒するようにもなった。パワーストーンを買い集め、ある時なんかは僕に「水晶に手をかざして何か感じるか答えてみろ」などと言ったりもした。朝には昨日予知夢を見たとか、なにか悪いものがくるとか、そういう話をよくしていた。
父の言動は日に日に不安定になっていった。
僕と妹に「創作することは素晴らしいことだから、色々やってみろ」と言ったのに、それからしばらくたって「そんなくだらないことはすぐにやめろ」と言う。それを言われた僕は自室に帰りながら「お前は僕の世界を壊した」とずっと呟いていたのを覚えている。そんなふうに昨日言っていることと今日行っていることが180度違うなんてことは、日常茶飯事だった。
とにかく振り回された。どうして父がそうなったかなど、子どもが理解できるはずもない。
非日常的な言動のすべてが嫌だったといえば嘘になる。スピリチュアルな話には正直ワクワクしたりもした。だがそれ以上に困惑した。その他の言動については言うまでもない。ただ怖かった。不安だった。落ち着かなかった。父の顔色一つで世界がどうにかなってしまうような気持ちを抱えて、日々怯えながら過ごしていた。ずっと不安で怖かった。
それから父は精神科に通うようになった。父から病名は「自律神経失調症」だと伝えられたが、どう考えてもそれが間違っていることは、知識のついた今ならよく分かる。極度の疑心暗鬼、妄想じみた思考、情動調整の不全、対人恐怖、爆発するような怒り方。どう考えても自律神経失調症ではない。
父に対して恐怖や嫌悪を強く感じるようになったのは、この頃からだった。
そして安全な場所がどこにもなくなってしまったのも、この頃だった。
家も、そして学校も、僕にとっては居場所ではなくなってしまったのだ。