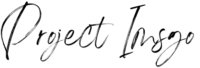ふと自分の内面に意識を向けると、そこにはいつも子どもの姿をした自分がいる。膝を抱えて真っ暗闇の中に座る、おそらくは小学校高学年くらいの自分の姿がイメージできる。そこは心の最深部のような場所で、他人は絶対に入ってくることができない。加害からは身を守れるが、救ってくれるものはなにもない。虚ろな場所だ。
そこに外側からはじめてやってきたのが、「佐藤愛」だった。
『80年生まれ、佐藤愛 ―女の人生、ある発達障害者の場合』は主人公である「佐藤愛」の半生を通して、その裏側に横たわるジェンダーロールの呪いや、不適切な養育、学校での虐待、DV、セクハラやパワハラなどの被害体験、そして発達障害当事者の生きづらさを克明に描き出している。
この投稿で書評を書くつもりはない。ただこの物語と僕の間で生じた現象について記したいと思う。
「愛」と「僕」の属性や境遇はもちろん完全に一致することはないが、描かれる体験は非常によく似ていた。まるでほんの少し中身の違うパラレルワールドの自分を見ているような気分だった。
読む前こそフラッシュバックに怯えてはいたが、読み進めるにつれて生まれた感情は「懐かしさ」だった。こんなふうだったよな、僕も。愛は僕にとって、孤独を分け合える友だちのような存在に思えた。
一気に読み終わってすぐ、作者であり友人でもある宇樹さんとやりとりをした。
「お互いあの頃出会っていたらまた違っていたかもね」
「一緒に話しながら帰れたら支えになったろうね」
そんな話をしながら情景を想像したら、涙が止まらなくなった。はじめぽろぽろこぼれていた涙は、やがて嗚咽に変わった。さながら子どもの自分が表層に出てきたかのような感じだった。
ああ、本当に僕は寂しかったんだな。
学校では教師や同級生からの虐待を受けていた愛は、当時の僕とよく似ていた。
いろいろなことを思い出した。
容姿のことでいじめられたこと。好きな子とこっそりやり取りしていた手紙を取り上げられ、教室の前、皆がいる場所で音読されたこと。首謀者の一人の顔面を殴り付けようと胸ぐらを掴んだのに拳に力が入らなかったこと。
家庭での僕もまた、愛に近しい孤独を感じていた。
勉強をしないといかに過酷な未来が待っているか、毎日のように父に聞かされた。気まぐれで居酒屋に連れて行かれ、酩酊した父を家までなんとか連れ帰った。その無様な父の姿と、惨めさと恥ずかしさを今でも覚えている。
社会とは恐ろしいところだ。愛は幼少期にそう刷り込まれていた。
「お前は特別だ。周りの奴らはみんな叩き潰せ」
僕もまた、そう言われて育った。
受験で苦しくて苦しくてしょうがなかった時、「つらかったな」ってその一言が欲しかった。けれど代わりに父が僕に与えたのは、自分の処方されている抗不安薬だった。端から見ればとんでもないことだが、その時の僕はそんなものでも救われた気になっていた。酒に酔う感覚を知らない子どもに抗不安薬のもたらす酩酊感は凄まじかった。体の力は抜けきり、立つのも難しい。だがそれがこの上なく心地良い。すべての苦しみから解放された感じがした。
思えば父は父なりに僕を助けようとしていたのかもしれない。そのやり方が絶望的におかしかっただけで。
心の最深部、真っ暗闇の夜の底にふわっと愛が現れる。
「君も頑張ってんだね」
愛は僕にそう言ってくれた気がした。
夕焼けの帰り道、川の土手を歩きながらふたりで「寂しいね」「つらいね」と言い合うさまを夢想した。重たい革のランドセルを背負った愛と、後ろからなんども蹴り飛ばされてぺちゃんこになったランドセルを背負った僕。時間と空間、現実を超えて僕らは出会えた。
僕は女性ではない。発達障害の当事者でもない。それでも愛とは多くを分かち合えた気がした。
だから僕は、あの日の「僕」にこういってやりたい。
「やっとともだちに会えたよ」と。