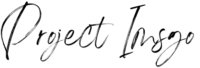つい先日、娘が1歳の誕生日を迎えた。妻と「手紙を書こう」という話になり、彼女が買ってきてくれた便箋を前にして僕はあることを思いついた。字が読めるくらいになった娘への手紙に加えて、いつか大きくなった娘へ宛てた手紙を書こう。そう決めて早速下書きを始めた。
未来に向けて手紙を書くというのは、実はありふれたことかもしれない。小学校とかで書く「将来の自分へ」とか、そういうもの。けれど僕は未来を想像することはあれど、具体的なメッセージとして何かを表現することはできなかった。
僕の時間はきれいに流れていなかった。時系列は断絶し、ところどころループし、混乱していた。過去と今が地続きであることを実感できるようになったのは、本当につい最近のことなのだ。長らくそのことは治療のテーマになっていた。カウンセラーによれば、トラウマやそれに匹敵するようないくつかの体験が、それぞれのポイントで自分史を遮断する「壁」となっていたのだという。現に僕の時間認識はその壁の前後で分断され、連続性を欠いていた。まるで繰り返し死んで、そのたび新しい自分にバトンタッチしてきたかのような感覚だった。
虫食いの自分史が修復され僕の中で正しい時間が流れ始めたのは、まさに娘が生まれてからだった。妻と娘が退院する時、ふと「2100年になってももしかしたらこの子は生きていて、80歳になっているんだな」と思った。そう思った瞬間、自分の存在が終わった後のその先に思いが向いたのだ。僕がいずれ死んだとしても、娘は生き続けるかもしれない。世界は続いていくかもしれない。それは至極当然のことなんだけれども、僕にとっては衝撃的な感覚だった。
次のカウンセリングでそのことを話した。そう感じるのは、今ここに私は私として生きているという実感があるからこそであり、自我境界がしっかりしてきた証拠だとカウンセラーは言った。なるほど。「今ここ」の感覚があってこそ、時系列は「列」として成立するのか。
尊敬する情報学者であるドミニク・チェンさんの著書「未来をつくる言葉」に、自分の娘に向けて遺書を書くというエピソードが登場する。僕が将来の娘に向けて言葉を残そうと考えたのも、この話に触発されてのことだった。
子に何かを託すということを、僕はどうしても好きになれない。それはたぶん、僕が嫌だったから。だから何か託したり願ったりするのではなく、「今この瞬間」の気持ちを率直に書いた。手紙の体をとってはいるが、他人が読むことを前提にした日記、つまりこのブログと同じようなものだ。
妻は両親に「世界中が敵になってもわたしたちは味方だから」と言われて育ったのだという。かつての僕はそれが妬ましかった。悔しかった。僕にはどうあっても得られなかった言葉を、彼女はずっと得続けていたのだから。隣の芝生は青く見える。だから燃やしてしまおう。当時の僕は口癖のようにそんなことを言っていた。そのくらい妬ましくて悔しくて、どうしようもなく惨めだった。
そして今ここに至り、僕は親になった。多くが変わった。多くに変えられた。だとすれば今の僕が自分の子に対して伝えるべきは、もう決まっている。
「僕はいつ、どんな時でも、どんな君でも、ずっと味方です」
こうあってくれと願うのではない。託すときれいな言葉を使いながら、その実何かを背負わせるわけでもない。ただ、今の僕が思う率直なことだった。そして言いたいことだった。だから僕は手紙を書き始める時、絶対にこの一文をいれようと思った。
書いた手紙は封筒に入れ、amazarashiのベスト盤に付いてきたステッカーで封をした。アルバムの名は「メッセージボトル」。そのタイトルロゴが印字されたステッカーがまだ残っていた。まさにぴったりじゃないか。いつかどこかの誰かが読んでくれたらいいな。そのくらいの淡い思いを綴って流すもの。僕にとってはいつかの娘に届いたらいいなと、時間の海に流すもの。
もしも「いつか」が今日の続きなら、この手紙もきっと届くだろう。そのことを願うくらいは、自分に許してやろうと思う。