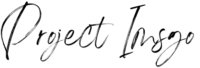罪とはやっかいな概念だ。主観的だし、文化や文脈によって定義も中身も変わる。だから「罪と罰を法によって定める」として刑法の類がつくられたわけだが、なにも法によって規定されたものが「罪」のすべてじゃない。法に触れない罪なんて、この世界に山のようにある。
今もどこかで誰かがそんな「罪」を犯し、誰かを、あるいは自分を傷つけている。そういう意味では潔白な人間など誰もいない。僕だってそうだ。これまで罪にまみれて生きてきた人間だ。
小学生の頃、ちょうど祖父が家で倒れて死んで、それをきっかけに父親がおかしくなり始めた頃だったか。母が花壇で世話していたチューリップの花を園芸用の棒で一本残らず刈り取ったことがあった。理由はもう覚えていない。春の家庭訪問の頃だったと思う。暴虐の限りを尽くした僕に対し、母は怒ることもなく「先生に見せたかったのにな」と残念そうに言った。その瞬間の罪悪感が未だに焼き付いている。
法によって定められたものはもちろん「罪」だが、それを規定に則って償ったところで、罪を犯した事実は消えないし、法的責任は全うしたとしても道義的な罪が同時に贖われるとは限らない。
だが法的な罪を犯し、それを背負って、覚悟を持って何かを成している人たちを知っている。
その一方で、法的な責任を果たしたことで満足し、己の罪の本質に向き合うことをしない人たちを知っている。
母のチューリップを皆殺しにした僕は、法的な罪に問われはしなかったが、「道義的な罪」に問われ続けている。当時暮らしていた家はもう取り壊されているから、母の花壇はもうない。それに小学4年生だか5年生だかの春の、家庭訪問の前の満開のチューリップという場面は再現性のない不可逆なものだ。取り返しがつかいないことの、取り返しのつかなさに責め立てられる。
たとえそれが気持ちの行き場を失った子どもの病的な行動だったとしても、自分で自分を許すことができない。
いつも春になると思い出す。僕はどうすればよかったんだろう。
答えはない。贖いの方法とは、与えられるものではない。
そしてこういう過剰なまでの罪悪感こそ、僕の病理そのものでもある。